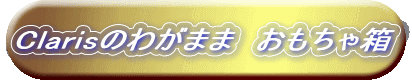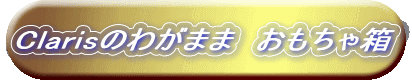|
|
|
◆ ベンチマークの実施 ◆
RedHat(linux)を使用するメリットとして、「少ないリソース(資源で)動作が可能・・・」と、言うキャッチコピーが近年叫ばれていました。
しかし、RedHat(linux)のバージョンが上がるたびに、より多くのリソースを消費している事も事実です。
この事は、その分使いやすくなる為、多くの機能が追加され消費するリソースも多くなっていることが上げられます。
最近のPCでは、CPU能力の向上、メモリー安価により拡張などあまりリソースを気にしなくてもよいご時世になりました。
しかし、
「使用しているPCの能力はどれくいだろう・・・・」
と、思うのは、当然の疑問です。
この事を客観的に、評価する方法の一つに、”ベンチマーク(テスト)”があります。
ベンチマークは、定量的な命令・処理等を実施することにより、テストマシンの性能を評価する指標の一つになります。
◆ ベンチマークソフトのダウンロード ◆
ベンチマークソフトは、色々ありますが、今回使用するのは、
HDBENCH clone を使用します。
該当のベンチマークソフトは、ベクターからダウンロード出来ます。
ベクターのページからダウンロードページにリンクしていますので、辿っていきます。現時点でのバージョンは、HDBENCH
clone 0.14.0 です。
また、今回ダウンロードしたファイルは、hdbench-0.14.0.tar.gz です。
該当のソフトを使用してテストできる項目は、
CPU/VIDEO/IMAGE/DISK 等の評価が出来ます。
操作も簡単で、ベンチマークソフトを起動するとx window上に、画面が起動されますので、ボタンをクリックするだけです。
◆ ベンチマークソフトのインストール ◆
1.ダウンロードファイルの解凍
適当なディレクトリーにダウンロードファイルを置きます。
今回のダウンロードファイルは、hdbench-0.14.0.tar.gz を使用しました。
以降の作業を実施するに当たり、まずは、root権限になります。
$ su -
$ Password:(rootのパスワード)
ダウンロードファイルの解凍は、
$ tar -zxvf hdbench-0.14.0.tar.gz
で、解凍することが出来ます。
該当命名を実行した場合のログは、こちら。
解凍が正しく出来ると、hdbench-0.14.0 と言うディレクトリが作成されます。
2.解凍後のコンパイル
正しく解凍が出来た後、ベンチマークソフトのコンパイルを実施します。
コンパイルを実施する前に、先ほど出来たディレクトリに移動します。
$ cd hdbench-0.14.0
該当ファイル中に存在するファイルとサイズ・権限は、この様になります。
その後、configureを実行します。
$ ./configure
該当命令を実行した場合のログは、こちら。
その後、makeを実行します。
$ make
該当命令を実行した場合のログは、こちら。
その後、make installを実行します。
$ make install
該当命令を実行した場合のログは、こちら。
以上で、インストールは完了です。
では、実際に実行してみましょう。
◆ ベンチマークテストの実行 ◆
ベンチマークの実行方法は、いたって簡単です。
今回使用するベンチマークソフトは、x windowを使用しますので、x window systemを起動します。
ターミナルを起動し、
$ hdbench
と、入力します。
そうすると、この様な画面が起動されます。
その後、"ALL"のボタンをクリックします。
クリック後は、各ハードウェアの測定が実行されます。
実行中は、この様な画面が繰り返し表示されます。
◆ ベンチマークテストの結果について ◆
測定が終了すると、各項目に値がセットされます。
該当の値が、ベンチマークソフトを実行したPCのベンチマーク結果となります。
以下に、それぞれの測定項目の意味を記述します。
CPUの結果
浮動小数点演算
1秒間あたりの浮動少数演算の計算回数
整数演算
1秒間あたりの整数演算の計算回数
メモリ
データの転送元と先にそれぞれ2MBずつのメモリを確保し、ダブルワードストリング転送で32KBのデータを64回転送を繰り返します。
32KBを転送するごとに計測値は、1を数え、計測は3秒間実施されます。
その結果が、該当値となります。
VIDEOの結果
短形
通常のXlibの描画関数(X Window System用標準ライブラリ)を用いて短形を描画します。
描画場所はランダムで、描画の大きさは、50×50ピクセルです。
該当の測定値は、1秒間あたりの描画回数を表します。
円
短形と同じく通常のXlibの描画関数を使用して、円を描画します。
描画場所はランダムで円の大きさは、直径50ピクセルです。
該当の測定値は、1秒間あたりの描画回数を表します。
テキスト
ランダムに"HDBENCH clone"と表示します。
該当の測定値は、1秒間あたりの描画回数を表します。
スクロール
画面全体を1ピクセル下にずらしコピーします。Y座標が0ラインに線を引くと言う処理を、繰り返しスクロールします。
50ピクセルをスクロールするごとに、計測値は1を数えます。
該当の測定値は、約3秒間あたりの描画回数を表します。
IMAGE
Ximageを使って1000枚のスプライトを縦横無尽に動かします。
該当の測定値は、1秒間あたりの書き換えたフレーム数です。
DISKの結果
READ
右側の"DRIVE"欄に指定されたパスにテンポラリファイルを作成します。
"使用容量"欄で指定されたサイズまで512KBずつ読み込みます。
該当の測定値は、1秒間あたりの転送バイト数です。
WRITE
右側の"DRIVE"欄に指定されたパスにテンポラリファイルを作成します。
"使用容量"欄で指定されたサイズまで512KBずつ書込みます。
該当の測定値は、1秒間あたりの転送バイト数です。
◆ ベンチマーク結果の参考値 ◆
自分のマシン上でのベンチマーク結果だけでは、
「一体、これらの数字って、速いの?遅いの?」
と、思うでしょう。
そこで、私が実測したPC上の結果を下記に表示します。
サンプル結果1
サンプル結果1で実行したPCのスペックは、以下となります。
| CPU |
Intel PentiumⅢ 1.0GHz |
| メモリ |
256MByte |
| DISK |
IDE接続(40GByte × 1基) |
|
|
| |
結果は、こちら |
サンプル結果2
サンプル結果1で実行したPCのスペックは、以下となります。
| CPU |
Intel Pentium MMX 200MHz |
| メモリ |
96MByte |
| DISK |
IDE接続(60GByte 計4基) |
|
|
| |
結果は、こちら |
|